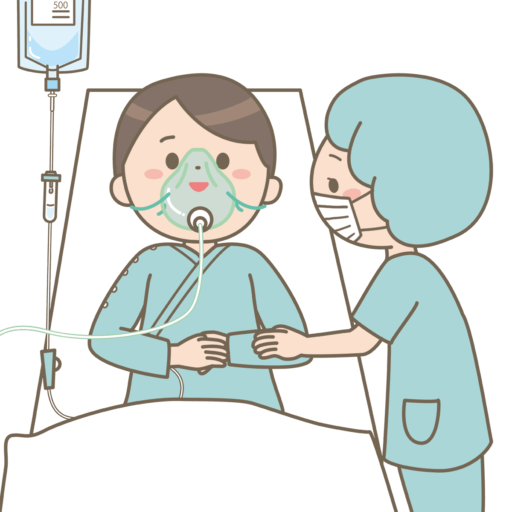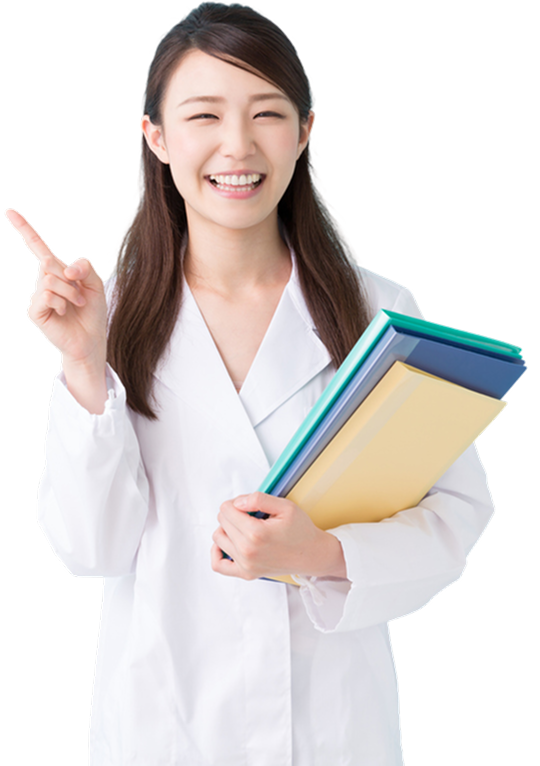吸入麻酔と静脈麻酔
医療において、麻酔は手術の成功と患者様の安全を支える重要な柱の一つです。麻酔法は大きく「吸入麻酔」と「静脈麻酔」の二つに分けられ、麻酔科の先生方は患者様の状態や手術内容に応じて最適な方法を選択しています。
吸入麻酔の特長
吸入麻酔は、セボフルランやデスフルランといった揮発性の麻酔薬を気化させ、ガスとして吸入させることで麻酔を維持する方法です。

メリット
【濃度管理の容易さ】
患者様の肺を通して麻酔薬の濃度を調整するため、投与するガス濃度を変更すれば、血中濃度が比較的早く、容易にコントロールできます。これは手術中に予期せぬ変化があった際の調整に優れています。
【高い安全性】
長年にわたる使用実績があり、安全性や薬理作用に関するデータが豊富です。
デメリット
【覚醒の遅延】
術後、体内に残った麻酔ガスが排出されるのに時間がかかる場合があり、覚醒に時間を要することがあります。呼吸機能が悪い場合、さらに麻酔ガスの排出が遅れることがあります。
【環境負荷】
一部の麻酔ガスは温室効果ガスであり、とくにデスフルランは地球温暖化の効果が大きく環境への配慮が課題となっています。
環境への配慮から、EUでは今後デスフルランの使用が規制される方向で進んでいます。
静脈麻酔の特長
静脈麻酔は、プロポフォールなどの麻酔薬を静脈から直接投与する方法です。
静脈麻酔にはTIVA (Total Intravenous Anesthesia:全静脈麻酔)という、吸入麻酔薬を使用せず、鎮静・鎮痛・筋弛緩をすべて静脈内投与で管理する全身麻酔法があります。
メリット
【速やかな術後覚醒】
薬剤の血中濃度が速やかに下がるため、術後の覚醒が非常にスムーズかつ迅速です。肝機能・腎機能が悪い場合、代謝・排泄に影響し、覚醒に時間を要することがありますが、一般的には、静脈麻酔の方が吸入麻酔と比較して覚醒遅延のリスクは低いと言われています。
【術後悪心・嘔吐(PONV)の軽減】
プロポフォールなどの静脈麻酔薬にはPONV抑制効果があるとされ、術後の不快感を大幅に軽減できます。

デメリット
【循環抑制作用】
静脈麻酔薬(とくにプロポフォール)は、血管拡張作用+心筋収縮抑制作用があり、初回投与時には急激な血圧低下を起こすことがあります。心機能が悪い場合、より慎重な投与と血圧低下・徐脈に注意が必要です。
【投与管理エラーのリスク】
投与経路の誤認やポンプ設定ミスが、血中濃度の急激な変動(過剰麻酔や術中覚醒)に直接つながるリスクがあり、厳重な確認が求められます。
バランス麻酔:吸入麻酔と静脈麻酔の併用
現在使用されている吸入麻酔薬や静脈麻酔薬は、単独でも高濃度で使用すれば、中枢神経を強く抑制して痛み刺激を抑制することができます。しかし、循環抑制作用が強くなったり、覚醒遅延したりなどの不利益が生じてしまいます。
そこで現在、ほとんどの手術では、吸入麻酔薬と静脈麻酔薬(鎮痛薬、鎮静薬、筋弛緩薬など)を適切に組み合わせたバランス麻酔が採用されています。
これは、単一の薬剤で、全身麻酔に必要な条件をバランスよく満たす麻酔薬はないため、複数の薬剤を組み合わせて単一の薬剤のみでは避けられないデメリットを、複数の薬剤で補うことを目的としています。
成人の麻酔導入ではプロポフォールなどの静脈麻酔薬で鎮静を行い、麻酔維持ではセボフルランなどの吸入麻酔薬で鎮静状態を維持する、というパターンが一般的です。
まとめ
麻酔科の先生方は、「吸入麻酔」と「静脈麻酔」を併用または使い分けることで、患者様にとっても麻酔チームにとっても、より安全で効率的な全身麻酔を実現しています。それぞれのメリット・デメリットをしっかり把握し、状況に応じて適切に選択することが重要です。